先生は農学部としては珍しい分野の研究に取り組んでおられるそうですね。
いろんな分野に取り組んでいるのですが、今回お話しするのは料理と色の関係についての研究です。料理というのは五味・五色・五法を五感で味わうと言われていて、五味とは、甘味、酸味、塩味、苦み、旨味です。五法とは調理法のことで、生、焼く、煮る、揚げる、蒸すのことを指します。このように料理は多くの要素で成り立っており、調理する側としてはできるだけこれらを駆使するとともに、食べる側もあらゆる感覚を働かせて味わうとより堪能できるということになります。そうした人間の感覚の中で、とりわけ「視覚」はダイレクトかつ瞬時に働きます。皆さんがコンビニで食品を買うとき、パッと見て選ぶことが多いですね。時間にして数秒とか。ですので、見た目は選択においても大事な役割を果たしていて、どう視覚的に訴えかけるかというのは、購買意欲を喚起するマーケティング面でも重要になってきます。その視覚を大きく左右するのが「色」です。私の研究テーマは食と色彩の関係——例えばコンビニ弁当のパッケージ色、コーヒーカップの色、テーブルクロス、トレイといった食環境における色彩が、視覚的なおいしさにどう影響を与えているか。それを調べています。

すごくよくわかります! では、調査されてきたことを具体的に教えてください。
「弁当パッケージの色が喫食者の購買意欲に及ぼす影響」の研究では、実際に多くの人に見てもらいながらアンケート調査を行いました。どういう調査をするかというと、商品やサービスの印象を調べるときによく用いる「エスディー法(SD法)」という方法で、「温かい—冷たい」「甘い—辛い」など対立する形容詞対を用意して、対象物から受けた印象をたずねていきます。調査で取り上げる商品に何を感じてもらいたいかを事前に検討したうえで、それに見合う形容詞対を数多くピックアップして調査に臨みます。
お見せするのは画面上のサンプルです。事前に市場調査をして嗜好性の高かったお弁当を選び、パッケージの色を様々に差し替えてそれぞれの印象を述べてもらいます。画面上なので正確な色じゃないと思うかもしれませんが、パソコン上の光源色を物体色と同様に見えるように色彩輝度計を使いながら細かく調整し、最後は目視で実際のモノと同じ見映えであることを確認しています。色もとても細かく種類分けしていて、同じ赤でもビビッドな赤、ダークな赤、ペールな赤という風に画像編集ソフトで調整していきます。このパッケージの調査は数年掛かりで、合計75色を調べ終えたばかりです。同じ製品で色だけを差し替えたほうが色の影響を正しく測れるので画面上で行いましたが、もちろん実物でしか調査できないケースもあります。テーブルクロス、ランチョンマットなどの敷物や、照明の影響を調べるときがそうですね。照明は細かく調整できる環境で照度を厳密に測りながら、部屋全体の湿度や温度にも気を配って調査をします。

コンビニ弁当の調査をされたきっかけは何ですか?
企業さんから問い合わせがあったんです。パッケージ製造を行っている企業さんなのですが、色の効果を教えてほしいと。それをきっかけに、これだけ食の外部化が進んでいるなか、忙しくても食事が味気ないものにならないように、おいしいと感じられる色、楽しい気持ちになるパッケージ等について研究してみたいと思うようになりました。かなりの労力をかけた調査ですので、やはり世の中に役立つにように、よりおいしく食べられるパッケージの提案につなげていきたいと考えています。

この研究なら、例えば病院食をよりおいしく見せる工夫など、医療や福祉施設で生活する人にも役立ちそうですね。
いい質問ですね。その分野も研究してきました。事例を紹介しますと、「給食用トレイの色がロービジョン者の視覚的なおいしさに与える影響」という研究にも取り組みました。視覚障害者向けの食器が製品としてあって、白いご飯を盛るための黒いお茶碗だったり、逆に牛乳のコップが黒だったり、白と黒は明度差が最も高いのでそのコントラストを利用して弱視の方が見えやすいようにしているわけです。でもそれを見て、どうも味気がないなと。もっと楽しい食卓にできないものかと感じて、研究を始めました。料理を載せるトレイは、料理自体に彩りがある場合とそうでない場合がありますので、その両方にアプローチする必要があります。ピンクなどのパステルカラーは、どんな彩りの料理を乗せても平均的においしく映ります。黄色は彩りの良い料理を、より一層おいしそうに見せてくれると同時に、どんな彩りの料理でもおいしく感じさせる効果がありました。視覚障害者の方にとってはやはり見えやすさが大事なので、その点ではオレンジが有効でした。オレンジは、食器には白が多いのでコントラストがついて視認性が高まり、さらにおいしそうに見える点でも評価が高かったですね。
トレイについては、高齢者施設でも利用者さんを対象に調査を実施しています。施設に学生が泊まり込んで、利用者さんと同じご飯を食べながら調べてくれたのですが、実際に食事を載せた状態で50人くらいから聴き取りました。その施設では普段、黒塗りのお盆を使って食事をされていたんです。黒塗りに勝るものはないとは思いつつも、ピンクのトレイで朝昼晩と食事をしていただくパターンや、朝と昼をピンクにして晩は茶色にするというパターンで印象を調べてみました。私はきっと黒の塗りのトレイがいいという反応になると思っていたら、実際には一番人気はピンクでした。ピンクはきれいだし食欲がわくという反応です。晩は落ち着いた色で食べた方がいいかもしれないと考えて茶色を試したのですが、施設の利用者さんは明るい色で毎回食べた方がおいしく感じるという興味深い結果になりました。
一般的に、ブルーは食欲をそそらない色だと捉えられていますよね。高齢者施設で約200名を対象に色に対する印象を調査をした結果、面白いことに、ブルーのトレイが「空みたいな色でいい」という意外な答えもあったのです。高齢者の方はあまり外出されない。だから自然の色に刺激を受けやすいようです。食卓の色はそんな役割も果たしてくれるという、私たちにない視点が参考になりました。
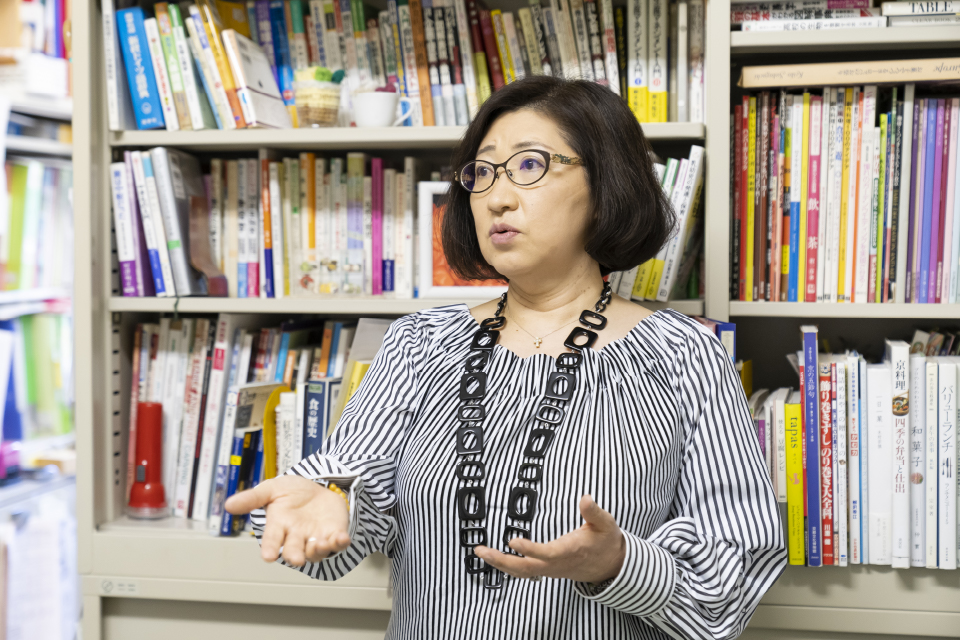
なるほど、対象者が違えば色に対する印象も全然違うんですね。私たちが普段の食生活で取り入れるとよい色ってありますか?
テーブルクロスを使うのであれば、赤や黄色など暖色系のビビットな色。これは大勢で食事をするときに会話の弾む色です。それからベージュは特にお勧め。ベージュは家族くらいの少人数で会話が弾み、さらに食事後もそこで少しゆっくりしたいと思わせるような色です。ですので、家族団らんのときは薄いベージュのテーブルクロスを敷くと効果的ですね。この調査もSD法で、実際にテーブルクロスを敷いた状態で座っていただき、そのときの心理状態を調べた結果得たデータです。ぜひご家庭で試してみてください。
この研究のやりがいは、どんなことでしょうか。
食べることは生きること。命のあるものは誰でも食べなければ生きられません。でも、私たち人間は生命維持のためだけに食べるわけではありません。コミュニケーションだったり、子どもなら心を育むことだったり、食べる意味はたくさんあって、そのなかでおいしく、楽しく食べるのはすごく大事な部分だと思います。それを演出していくうえで、色というのは重要な要素です。食事にいい色を取り入れることで、笑顔が生まれたり、心が癒されたりする。そんな状況をつくれるような研究成果を発信していきたいと考えています。人間には特別な日である「ハレ」と、日常の「ケ」があります。誕生日などにケーキを食べる人は多いでしょうが、今は「ケ」の日でもケーキは口にするし、「ハレ」と「ケ」の食にメリハリがなくなってきている状況もあります。きょうはスペシャルな日だから、色のいいランチョンマットを敷いてみようなど、そういう工夫にも色を使うことができます。ちょっとした楽しみや切り替えのために、食卓に色を取り入れてもいただけるようになると、とてもうれしいですね。






