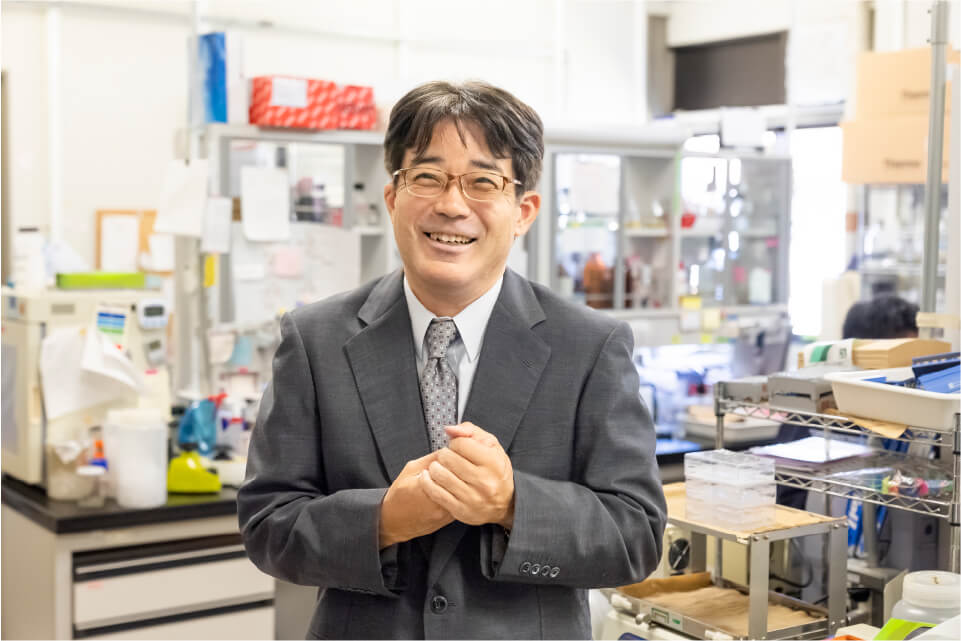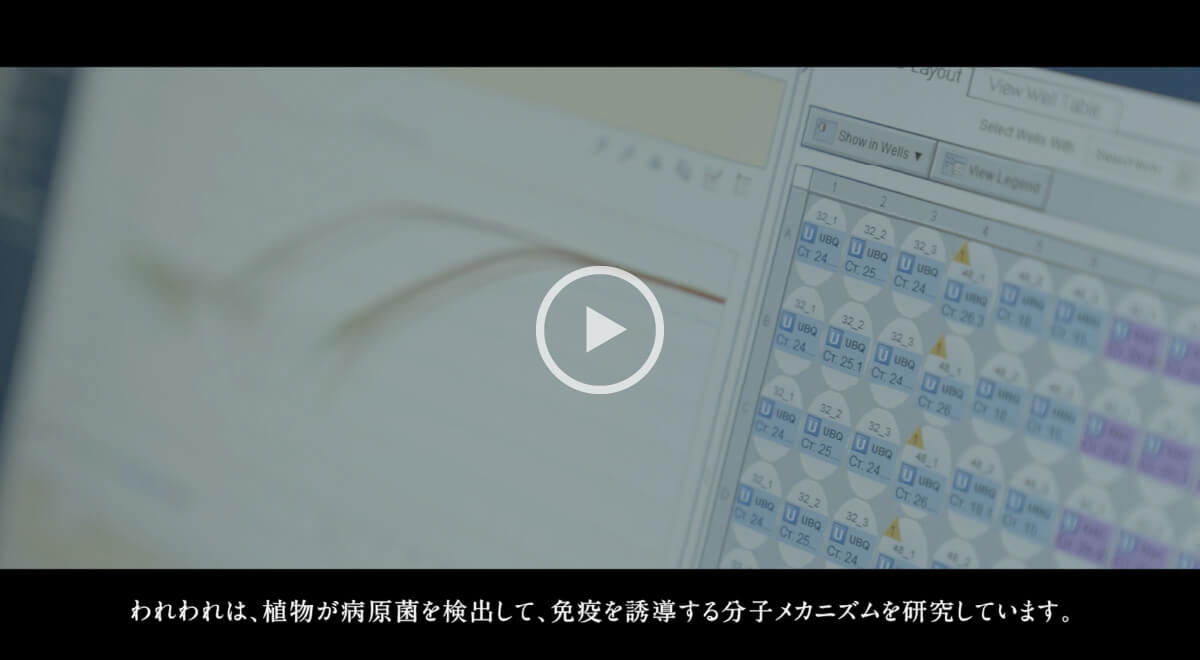生物機能科学科
2023/1/18
植物が持つすぐれた免疫機構を研究。
その成果を応用した新しい耐病性品種の開発をめざす。
川﨑 努 教授/植物分子遺伝学研究室
先生は農作物の病気に関することを研究されているんですね。
はい。植物が持つ病気に対抗する能力について研究しています。植物の周りには実にさまざまな微生物がいて、その中には病害を引き起こす病原菌もいれば、土壌の栄養分を吸収しやすくしてくれる共生菌もいます。共生菌としてよく知られているマメ科植物に付く根粒菌では、この菌が根っこに感染することで植物に窒素が供給されるしくみになっています。一方で植物は光合成で産生した栄養分を共生菌に与えていますので、両者は持ちつ持たれつの関係です。
植物は、自身にとって必要な共生菌を受け入れ、病原菌をやっつけないといけないんです。実は、植物はそれらの微生物をちゃんと区別しているんです。病原菌は植物の葉の気孔や根、あるいは葉の傷跡から入ろうとするなど、いろんなルートで植物に侵入しようとしてきます。それに対して植物は、細胞表面に微生物を検出する「病原菌認識センサー(受容体)」をたくさん備えていて、そのセンサーが菌の構成成分をキャッチすることで、病原菌か共生菌かを区別しています。植物は病原菌が近づくと、素早く防御応答を誘導するのですが、我々の研究室ではその過程で働いている遺伝子について調べています。
一般に農作物に病気が出たら農薬で対処するというイメージがあるかとおもいますが、本来は植物自身が感染を阻止するための防御機構を持っていて、潜在的には非常に強い戦う力を保持しています。研究を通じてそのメカニズムを解明できれば、応用技術として新規の耐病性植物を開発することにもつながります。耐病性が高ければ農薬の使用量も減るので、環境にもやさしい農業を実現できるということです。
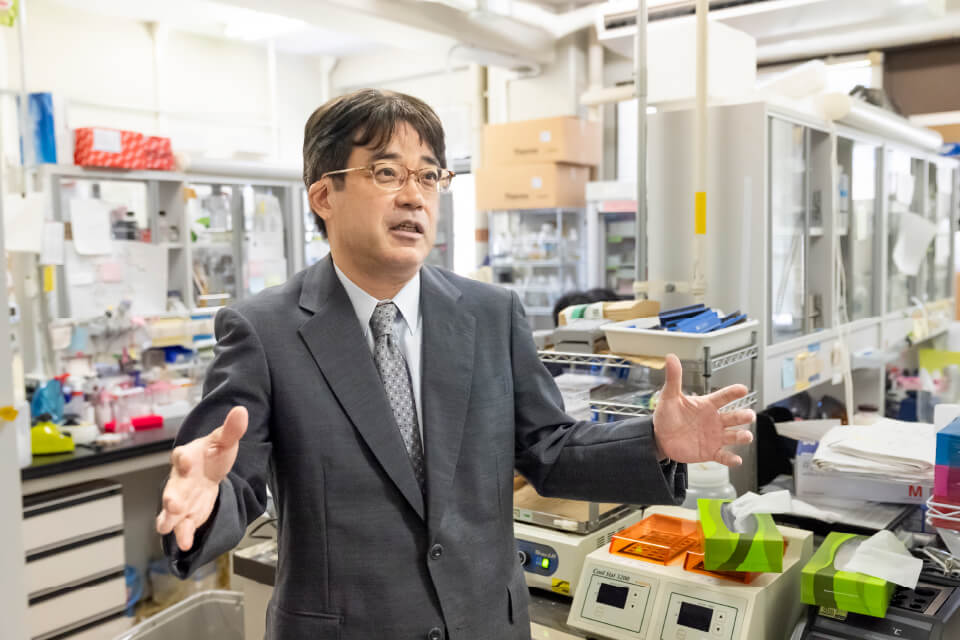
植物にそんなすごい免疫機構があるんですね! では、感染しようとする病原菌はそれに対してどう反応するんですか?
病原菌としては当然、それを抑えにかかります。病原菌側の戦略は、自らのタンパク質を植物の細胞内に分泌することによって、免疫反応の誘導を阻害しようとします。この分泌タンパク質は「エフェクター」と総称されています。病原菌は植物に対してエフェクターを出し、植物の免疫反応を止めて自らが増殖しやすい環境をつくろうとします。
例えば、水稲の病気である白葉枯病菌が出すエフェクターは、稲の糖輸送体遺伝子をハイジャックし、イネに糖輸送体をたくさん作らせます。そうすることで細胞の外に糖をどんどん排出させ、病原菌のほうに栄養を送り込むということをします。
我々はエフェクターの研究も行っており、病原菌がエフェクターを使って、どのように植物の免疫機構を止めているのかを調べています。エフェクターの働きがわかれば、それを阻止する方法を考えればいいというわけです。
植物と病原菌の目まぐるしい攻防があるようですが、植物は病原菌のエフェクターにも抵抗しているのですか?
植物にはエフェクターを検知して強い防御反応を誘導する「エフェクター誘導免疫」という機能も備わっています。植物のセンサーにも2種類あって、1つはすでにお話しした細胞表面に存在する病原菌認識センサーです。病原菌はエフェクターを使って、そのセンサーによって誘導される免疫反応を止めようとしますが、植物はもう1つ、エフェクターを検出する「NB-LRR型受容体」というセンサーを持っています。こちらは一層強力で、エフェクター誘導免疫では、自分の細胞を殺して、相手もろとも殺してしまいます。これは病原菌に殺されるのではなく、自分で自分の一部を殺すプログラム細胞死、要するに自爆です。

植物がここまで巧妙な防御反応を持っているとは驚きです。しかし農産物の病気は絶えないですね。
これは授業で学生にも言うことですが、この場に100人いたら皆、顔も形も違う。それぞれ遺伝子が違うし免疫力も異なるので、一人が病気になっても隣の人にうつるとは限りません。しかし農業には特有の状況があって、田んぼに植えられたイネは、コシヒカリならすべてコシヒカリです。遺伝子型が全部同じなので、田んぼの中の一つの個体に感染できる病原菌が発生すると、全てに感染してしまいます。このような病原菌は、エフェクターが変異することにより作られます。植物のNB-LRR型受容体は、エフェクターと結合することによって認識しますが、その結合は、カギとカギ穴の関係になっており、非常に厳密にできています。カギ穴の形がわずかでも変化してしまうと認識できず、免疫は誘導されません。もちろん病原菌も常に進化を続けており、その過程でエフェクターの形を変化させますので、仮に10年間かけて耐病性育種をつくったとしても、たった3~4年で菌の進化に打ち破られて、田んぼ一面が病気になってしまうようなことが起こり得るんです。
植物と微生物の間の相互作用というのは、いたちごっこの側面があり、植物が病原菌に勝てるようになったら、病原菌はエフェクターを新たに開発するなどしてそれを乗り越える。するとまた植物が進化する。そのような歴史を繰り返してきました。
だから農薬を使うということになるわけですね。
農薬は大きくわけて2種類あります。一つは昔からある病原菌を直接殺すタイプで、これは周りいる良い菌(共生菌)まで殺してしまうので環境に悪く、ヨーロッパを中心に規制が厳しくなっています。もう一つ、近年注目されているのが植物免疫活性剤と呼ばれるタイプの薬剤で、植物自身が免疫を活性化させて病気に強くなる農薬です。なぜ強くなるのかという作用機序はまだよくわかっていないのですが、今では多くのメーカーが製造しています。それでも青枯病菌など防げない病原菌もあります。やはり我々としては、農薬に頼るのではなく、植物と病原菌の攻防メカニズムの研究から得られた成果を、耐病性を高める育種に役立てていきたいと考えています。
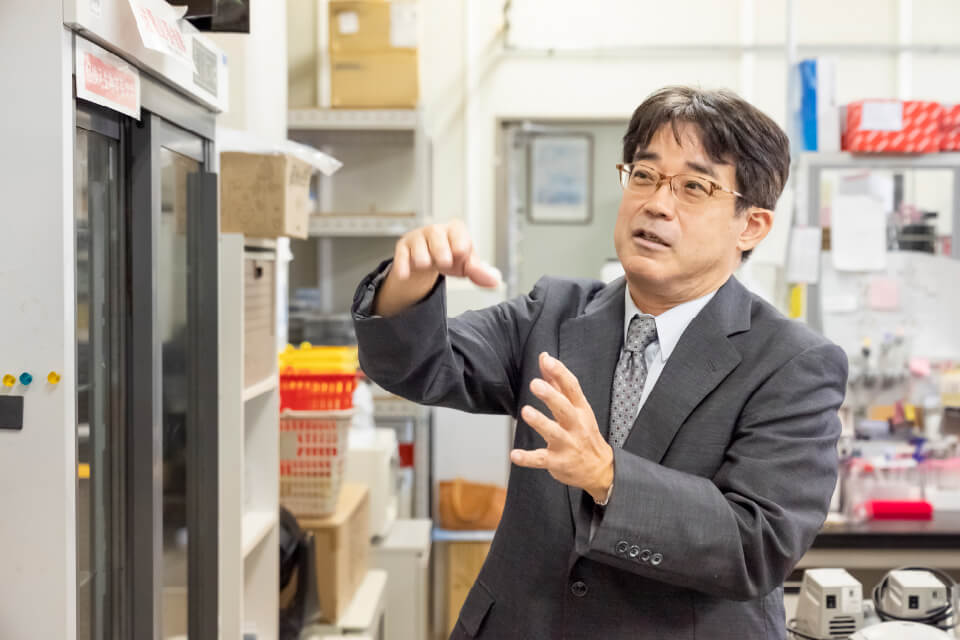
耐病性の高い植物につながるような研究の事例を教えてください。
最近、我々の研究チームが、水稲が「成長」と「耐病性」のどちらにエネルギーを使うのか、その切り替えのしくみを発見しました。水稲は病原菌に感染すると、あるタンパク質が活性化して免疫を高めます。このタンパク質は普段は働かない状態にあり、過剰に働くと成長が妨げられます。このメカニズムはわかっていませんでしたが、我々は別のタンパク質が活性化のスイッチになっていることを突き止めました。水稲は通常時、スイッチのタンパク質が免疫を高めるタンパク質の働きを抑制し、エネルギーが免疫に注がれるのを防いでいます。ところが病原菌に感染すると、ある酵素の働きによってスイッチのタンパク質を分解して、免疫を高めるタンパク質が働きだします。つまり、普段は成長にエネルギーを使い、病原菌をキャッチすると免疫にエネルギーが向く。このようなオン・オフの切り替えを行っていることがわかりました。ゲノム編集や品種改良などで両方のタンパク質を多く持つ植物をつくることができれば、耐病性が高いうえに収量の安定した品種になります。農薬の使用量を減らすことにもなるでしょう。
我々はモデル植物として、研究の世界公用語である水稲を使って研究を進めていますが、センサーが微生物を区別して防御応答を誘導するしくみはどの植物でも同じです。したがって、得られた成果は、他の植物にも利用できます。

病気に強く収穫も安定した品種が開発されると、農業に貢献できますね。
現在、農業生産のおよそ15%が病気で失われています。世界規模にすると、年間で10億人分くらいの食料が病気で失われていることになります。2050年には世界の人口が100億人を突破すると言われ、そうなると1.6倍もの食料が必要とされています。そのような状況にあって、いかに病気を抑えるかが「農学」として重要な課題です。植物免疫の基礎研究を通じて、農業の病気克服に貢献したいと考えています。