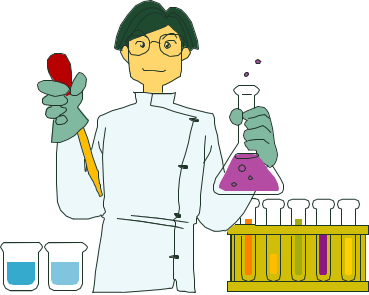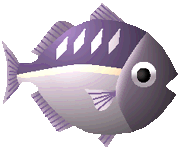【研究分野】
水産生物の遺伝と育種に関する研究/魚類の発生機構に関する研究/性統御と性分化機構の解明に関する研究/水産生物の機能遺伝子発現と生理機能に関する研究/細胞移植技術開発の育種学的利用に関する研究/トランスジェニック魚の作出と利用に関する研究
【研究方針】
魚類の品種改良、育種技術開発の基礎としての、細胞工学、遺伝子工学分野の研究を推進したいと思います。魚類養殖向けの究極の品種を作るべく、その基礎分野の構築を行おうとしています。魚類のDNA多型研究も、生物の多様性の解明のみならず、品種作出のための基礎データ集積の一環としても位置づけています。
【最近の研究紹介】
□ クロマグロの借腹生産技術体系の開発
クロマグロのような大きな魚になると、次世代を作出するための親魚を何百尾も養成するのは大変です。でも、少ない親から世代交代を繰り返していると、いわゆる「遺伝的多様性の減衰(血が濃くなり過ぎる)」ということがおきて、魚が病気にかかりやすくなったり、大きくなれなかったりするかもしれません。そうならないように、いまの元気な(遺伝的多様性を保持した)マグロの卵や精子のもとになる細胞(始原生殖細胞)を取り出し、保存して、それを必要なときに復活させることができるような技術が必要です。このためには始原生殖細胞を他の細胞と区別したり、生きたまま凍結保存したり、他の魚種の卵巣や精巣に入れて卵や精子に分化させたり、といった技術が必要です。
□ 水族館継代希少淡水魚群の遺伝的多様性維持
近年、絶滅に瀕する淡水魚種は多く、これらのほとんどは水族館や博物館に系統保存されていることが多いのですが、少数親魚による長期間の継代によって、遺伝的多様性が失われていることが懸念されています。これらは実際どのような状況にあるのかをモニターし、その対策を立てるためのデータを集めています。また、実際に多様性を失わないようにする継代法についても検討しています。
□ 遺伝子改変と遺伝子機能解析に関する研究
短期間に様々な遺伝子の発現系を作出できる系を作るために、別種の魚の成長ホルモン遺伝子を導入することによって、対象種の成長を促進して遺伝子改変系統の早期作出ができる実験系をつくっています。現在、4系統の成長促進系ができていますが、今年はこれらの純系化をおこなおうとしています。さらに促進効果の高い遺伝子コンストラクトの開発も行っています。トランスジェニック技術は様々な分野へ応用でき、水質を検査するバイオアッセイ系としても注目されています。外部環境の変化に対して体内で起こる様々な現象を体表から検出できる遺伝子発現検出システムを備えた実験魚の作出を検討中です。
□ 性決定と性分化機構
魚の性は基本的には生まれながらに決まっていますが、成長の過程で受ける環境からの様々な刺激で生まれつきの性とは異なった性機能を持つことがあります。種によってはそれが思いの外頻繁に起きているようです。そのメカニズムを解明するために、性決定に関与する遺伝子の単離(クローニング)と機能発現解析を行っています。
□DNA分析による琵琶湖産魚類の種判別
琵琶湖産モロコ類、ヒガイ類の簡易種判別法の開発を行っています。親は形態から容易に判別がつく種類も、仔稚魚期には形態からの種判別が困難です。ミトコンドリアDNAの一部の配列を使って分類できれば、仔稚魚期の生態を解明することに役立ちます。
【担当科目】
〔学 部〕 魚類発生生物学(3年後期),水産学基礎実験Ⅰ・Ⅱ(1,2年前期配当,生物分野担当),生物学実験(3年後期配当,遺伝学、発生学担当) 水産生物学実習, 基礎ゼミ、専門演習Ⅰ・Ⅱ,卒業研究
〔大学院〕 魚類発生生物学特論,水産細胞工学特論,魚類発生生物学演習,水族育種学実験
← ここをクリック